さいたま市ゆかりの文学者たち
○さいたま市出身の作家・文学者(石井桃子はこちらへ)(おかべりか はこちらへ)
○さいたま市に在住していた(している)作家・文学者(瀬田貞二はこちらへ)(斎藤惇夫はこちらへ)(大西民子はこちらへ)
○さいたま市が舞台になった文学作品(主なもの)の作者
- 『普門院さん』(井伏鱒二)
- 『誘拐ラプソディー』(荻原浩)
- 『あゝ玉杯に花うけて』(佐藤紅緑)
- 『歳月』、『雑木林と麦畑の中』(沢野久雄)
- 『雨月抄』(長谷川かな女)
- 『冬日の道』、『自伝抄Ⅷ』(水上勉)
- 『ランドマーク』(吉田修一)
- 『長英逃亡』(吉村昭)
人名の表記とヨミは「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス」に依ります。
人物画像は国立国会図書館デジタルコレクション「近代日本人の肖像」から、書影画像はBOOKデータASPから引用しています。
佐藤紅緑(さとう こうろく) 1874(明治7)年~1949(昭和24)年
 |
佐藤紅緑は青森県出身の小説家、俳人、劇作家です。詩人のサトウハチロー、作家の佐藤愛子の父でもあります。
1894年に日本新聞社に入社し、同僚の正岡子規の勧めで俳句を作り始めました。雅号である「紅緑」は子規から送られたものです。退職後に脚本や小説の執筆を始め、『時事新報』『読売新聞』に連載小説を発表する等、大衆小説の人気作家・人気劇作家となっていきました。
1927年から『少年倶楽部』で連載を開始した小説『あゝ玉杯に花うけて』は、浦和を舞台にして、けんかあり、いじめあり、先生との交流ありと、昭和初期の子どもたちの様子が垣間見える作品です。
浦和中学は古来の関東気質(かたぎ)の粋として豪邁不屈(ごうまいふくつ)な校風をもって名あるが、この年の二年にはどういうわけか奇妙な悪風がきざしかけた。それは東京の中学校を落第して仕方なしに浦和へきた怠惰生からの感染であった。
引用:『あゝ玉杯に花うけて』 佐藤紅緑/[著] 講談社 2014年 P73-74

平野万里(ひらの ばんり) 1885(明治18)年~1947(昭和22)年
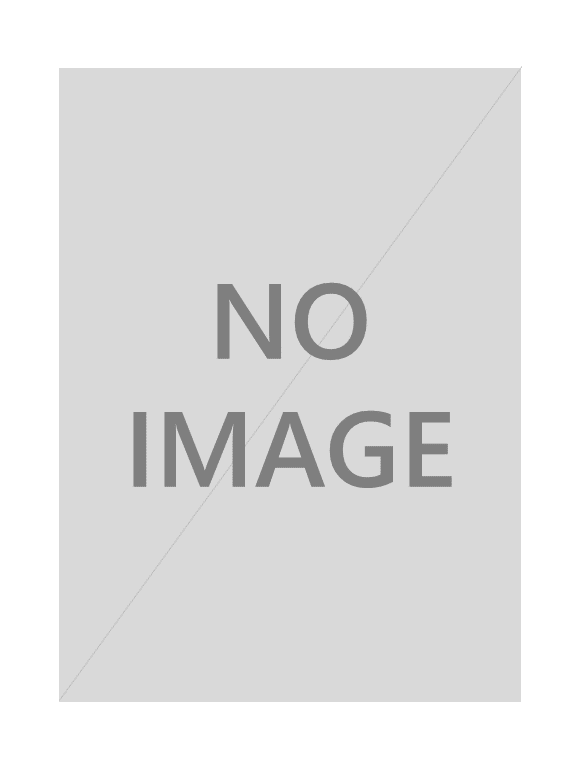 |
歌人・詩人の平野万里は、埼玉県北足立郡大門町(現さいたま市緑区)に生まれました。その後、北足立郡西遊馬村(現さいたま市西区)、東京市本郷区森川町(現東京都文京区)に転居しています。母が森鴎外の長男を里子として預かった関係で、森家へ出入りすることも多かったようです。
1901年に新詩社に入社し、翌年『明星』に長詩や短歌が掲載され始めました。1906年には、子どもの頃から縁の深い鴎外を、新詩社月例歌会に誘います。1907年、歌集『若き日』を刊行、翌年『明星』が廃刊したのち、後継誌『スバル』の発刊に関わります。1921年には、与謝野鉄幹・晶子夫妻らとともに新機関誌『明星(第二期)』を発刊しました。1922年に鴎外が死去し、『鴎外全集』の編集にあたります。
1942年に与謝野晶子が死去してからは、晶子遺稿歌集『白櫻集(はくおうしゅう)』や『晶子秀歌選』の編集にあたりました。万里が死去した翌年には万里の遺稿となった『晶子鑑賞』が刊行されています。

長谷川かな女(はせがわ かなじょ) 1887(明治20)年~1969(昭和44)年
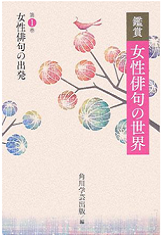 |
長谷川かな女は東京生まれの俳人です。
夫を亡くして間もなく、東京・新宿の自宅が火事で焼失したため、1928年に、息子とともに浦和市岸町に移住してきました。
引っ越し後、新しい土地に慣れていった心情を、『雨月抄』では、こう回想しています。
「冬ざれて焚く火に凹む大地かな」 大地、土、を、埼玉に来て始めてよく見た気がした。少しづつ自分の句がこれまでと変わって来るように覚える。
引用:『長谷川かな女全集』 長谷川かな女/著 東京四季出版 2013年 P532
1930年に俳句雑誌『水明』を創刊。他に句集として『龍膽(りんどう)』、『胡笛』、随筆に『小雪』、評論『加賀の千代』などがあります。
浦和区の調神社(つきじんじゃ)と、南区の別所沼のほとりには、句碑があります。

霜田史光(しもた のりみつ、しもた しこう) 1896(明治29)年~1933(昭和8)年
 |
霜田史光は詩人、小説家で、北足立郡美谷本村松本(現さいたま市南区)に生まれました。1919年に詩集『流れの秋』を刊行。剣豪小説『日本十大剣客伝』を発表するほか、野口雨情(のぐち うじょう)との共著『日本民謡名作集』や吉川英治との共著『寛永武鑑本伝御前試合』を著しています。童話作家としても知られ、1926年には、ジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』を児童向けに翻訳した本が出版されました。
やがて柳澤氏の発案で太田窪に鰻を食ひにゆくと云ふことに一決した。(中略)行く行く路端には野菊が咲いてゐたり、芒が並んでゐたり、柿の木に赤い柿が平和さうに枝垂れて、なってゐたりなぞして、事々に一行を喜ばしてゐる。
引用:『評伝霜田史光』 竹長吉正/著 日本図書センター 2003年 P132-133 『詩王』第二年第一号所収「六号雑記」より

井伏鱒二(いぶせ ますじ) 1898(明治31)年~1993(平成5)年
 |
井伏鱒二は広島県深安郡加茂村(現福山市)出身の小説家です。中学時代は画家を志していましたが、早稲田大学の学友から影響を受けて小説創作活動に励むようになりました。
『山椒魚』や直木賞受賞作である『ジョン万次郎漂流記』、映画にもなった『黒い雨』など、名作が多数あります。
さいたま市に関係が深い小説では『普門院さん』が有名です。1949年に発表された作品で、幕末に活躍した小栗上野介の最期について描いたものです。
寺の住職が真実をつきとめるという設定になっていますが、そのモデルになったのが、普門院の第四十二世住職であった阿部道山和尚です。普門院は1426年に創建された、さいたま市大宮区大成町にある曹洞宗のお寺で、元は、領主の金子駿河守大成(かねこするがのかみおおなり)が居城であった大成館を寺院にしたといわれています。

神保光太郎(じんぼう こうたろう) 1905(明治38)年~1990(平成2)年
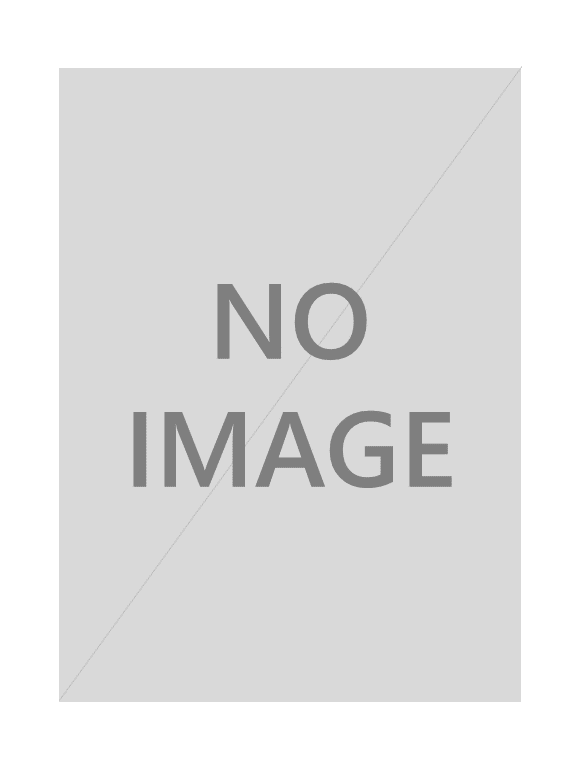 |
神保光太郎は山形県に生まれた詩人です。
学生時代から詩作を始め、1935年に『日本浪曼派』の創刊に参加し、その後も詩誌『四季』などに作品を発表しました。詩集には、第一詩集『鳥』や『青の童話』などがあります。1935年から浦和市の別所沼の近くに移り住み、終生この地を活動の拠点としました。
1956年の埼玉詩人クラブ(現埼玉詩人会)の発足に際しては初代会長となりました。また1968年に創刊した『文芸埼玉』の初代編集委員長を務めるなど、戦後埼玉の文学界の発展に大きな足跡を残しました。
1982年には、別所沼に詩碑が建てられています。
ー孤独ー
沼のほとりをめぐりながら
神をおもふ(後略)
引用:『さいたま文学案内』 埼玉県高等学校国語科教育研究会/編 さきたま出版会 1996年 P10 「冬日断抄」より

沢野久雄(さわの ひさお) 1912(大正1)年~1992(平成4)年
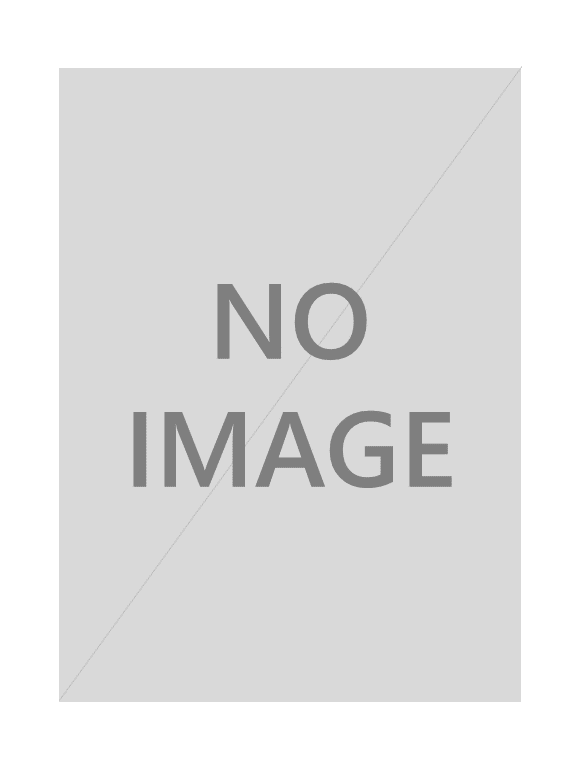 |
沢野久雄は埼玉県浦和町(現さいたま市)出身の小説家です。埼玉県立浦和中学校(現埼玉県立浦和高等学校)を経て、第二早稲田高等学院(現早稲田大学)国文科を卒業しました。卒業後、都新聞社に入社し数年勤務の後、朝日新聞社に移り勤務しながら小説を発表しました。
1950年に『挽歌』が芥川賞候補となり、その後も、『方舟追放』、『夜の河』、『未知の人』が候補となりましたが、受賞には至りませんでした。なかでも『夜の河』は、1956年に映画化され代表作となりました。
1959年に専業作家となり、新聞への連載や『小説川端康成』、『生きていた─「ガン」からの生還─』など多数の作品を発表しました。
浦和にゆかりの作品としては、『歳月』、『雑木林と麦畑の中』があります。
一面の麦畑で、はるかに雑木林が見える。その上に秩父の連山がつづいて、富士が秀麗な姿を見せている。私は麦畑のほとりを通って、毎日、富士を見ながら小学校に通った。
引用:『さいたま文学案内』 埼玉県高等学校国語科教育研究会/編 さきたま出版会 1996年 P19 随筆「酒場(バア)の果汁(ジュース)」より

大木実(おおき みのる) 1913(大正2)年~1996(平成8)年
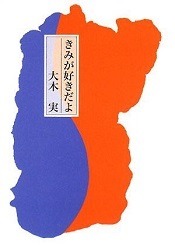 |
大木実は東京の本所に生まれた詩人です。太平洋戦争から復帰後、一時本庄に住んだのち転居し、大宮市上小町に居住していました。大宮市役所に勤めながら詩作に取り組み、1939年に『場末の子』を刊行。退職後は鴻巣に転居して詩を書き続け、『屋根』、『冬の支度』など多くの詩集を世に送り出しました。
埼玉詩人会や大宮詩人会の立ち上げや運営にも深く関わっています。
列車は停まる / 六番線上りホーム / 高崎発上野行 / 多くのひとが降り多くのひとが乗る / ――僕には通過駅 大宮
引用:『大木実全詩集』 大木実/著 潮流社 1984年 P717 詩「通過」より抜粋

立原道造(たちはら みちぞう) 1914(大正3)年~1939(昭和14)年
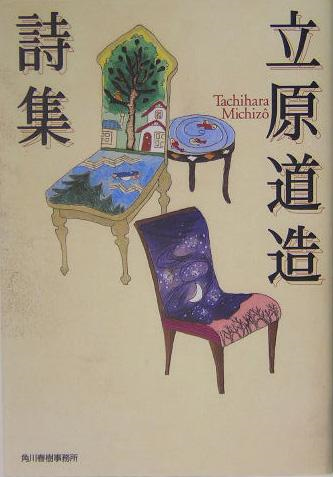 |
立原道造は東京生まれの詩人・建築家です。
13歳の頃に詩人の北原白秋を訪問し、口語自由律短歌を発表するなど、若いころからその才能を発揮しました。高校時代も詩作を続け、1939年には、第1回中原中也賞を受賞しています。詩集に『萱草(わすれぐさ)に寄(よ)す』や『優しき歌Ⅰ・Ⅱ』などがあります。また、建築家としても、東京帝国大学工学部在学中には、建築の奨励賞である辰野賞を三度受賞しています。
1939年に24歳の若さで亡くなりますが、見舞いに訪れた友人たちに語った「五月のそよ風をゼリーにして持って来て下さい」という言葉が有名です。
2004年、南区の別所沼公園に、かつて立原が設計した「ヒアシンスハウス」が建築されました。詩人・神保光太郎と親交があり、敬愛する神保の家近くに自分の住まいを建てたいと願い構想した夢が長年の時を経てついに実現に至ったものです。

水上勉(みなかみ つとむ、みずかみ つとむ) 1919(大正8)年~2004(平成16)年
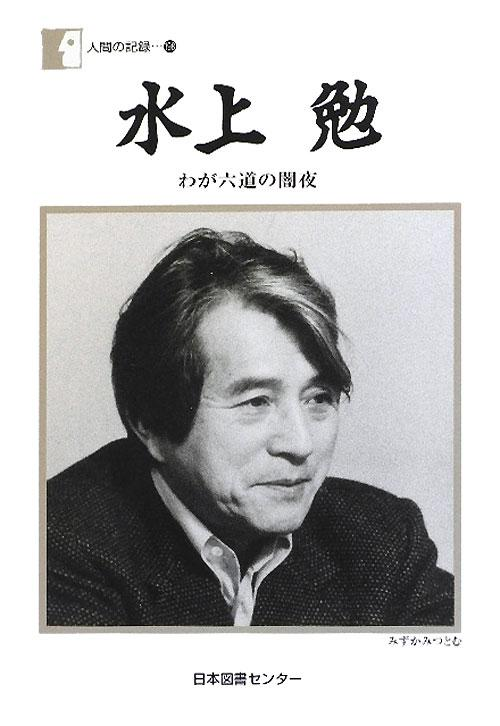 |
水上勉は福井県生まれの小説家です。
少年時代に禅寺で生活をしており、その当時の体験を元に、直木賞を受賞した『鴈の寺』という作品を生み出しています。
第二次世界大戦後、数年間浦和市に住んでいました。その当時に描いた私小説が、デビュー作となった『フライパンの歌』で、1948年に発行され、ベストセラーとなりました。
1970年出版の随想『冬日の道』では、作者が上京した昭和10年代から戦後に至るまでの生活状況が回想され、浦和に住んでいた頃の描写もあります。
また、1980年に出版された『自伝抄Ⅷ』では、「浦和にいた頃」と題して、浦和に住んでいたころの様子が詳細に描かれています。

宮沢章二(みやざわ しょうじ) 1919(大正8)年~2005(平成17)年
 |
宮沢章二は埼玉県羽生市生まれの詩人です。東京大学文学部美学科を卒業後、大宮市吉野町(現さいたま市北区)に住んでいました。
詩と共に童謡・歌曲・合唱曲などの歌詞も書き、全国各地の小中学校や高校の校歌を300校ほど、さいたま市内の小中学校でも約20校の校歌を作詞しました。また、クリスマスソング「ジングルベル」の歌詞も有名です。1972年に第2回日本童謡賞を受賞し、1990年度には地域の教育行政への貢献により大宮市文化賞を受賞しました。
主な詩集に『空存(くうぞん)』、『枯野抄』、『埼玉風物詩集』、『青春前期の君たちへ』が、童謡詩集では『知らない子』、『むぎばたけ童謡集』があります。
2011年の東日本大震災後には、「行為の意味」という詩の一節がCM広告として使用されました。

吉村昭(よしむら あきら) 1927(昭和2)年~2006(平成18)年
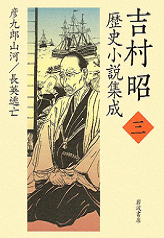 |
吉村昭は東京生まれの作家です。1966年に『星への旅』で第2回太宰治賞を、1973年には第21回菊池寛賞を受賞しました。
ドキュメント作品や歴史小説を多く発表し、1984年発表の『長英逃亡』は蘭学者高野長英が江戸の牢屋を脱獄し、逃亡する様を描いた小説です。主人公が日本中を逃亡する中で浦和や大宮の地へ逃げ込んだ様子が描かれています。
「浦和の兄のもとにお移りください。ここは危険です。」
水村が、口早やに言った。
兄とは、武州足立郡大間木村(埼玉県浦和市大間木)で代々医療にしたがう髙野隆仙で、長英も、水村の家から浦和へ行きたいとひそかに考えていたので、その申出に異存はなかった。
引用:『吉村昭歴史小説集成 第三巻』 吉村昭/著 岩波書店 2009年 P313

大谷羊太郎(おおたに ようたろう) 1931(昭和6)年~2022(令和4)年
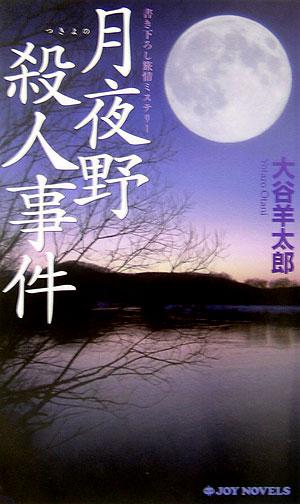 |
大谷羊太郎は東大阪市で生まれ、浦和市で育った推理作家です。埼玉県立浦和高等学校卒業、慶應義塾大学を中退しています。大学時代からプロミュージシャンとして活躍し芸能マネージャーとなりますが、その後、江戸川乱歩賞への応募を始め、推理小説家に転向した異色作家です。
1966年、『四つのギター』が第12回江戸川乱歩賞候補となり、1968年に同賞候補となった『死を運ぶギター』(『美談の報酬』を改題)で作家デビュー、翌年の『虚妄の残影(きょもうのざんえい)』も候補となります。1970年、『殺意の演奏』が第16回江戸川乱歩賞を受賞し、翌年より専業作家に転向しました。
芸能界やミュージシャンの体験を生かした本格ミステリーを始め、トラベルミステリー、時代小説まで、多数の作品を執筆しており、代表作に、『真夜中の殺意』、『大密室殺人事件』などがあります。
後年、さいたま文藝家協会賞選考委員を務め、浦和スポーツ文学賞(現さいたま市スポーツ文学賞)では1994年の創設当初から選考委員を続けられました。また、2005年にはさいたま市文化賞を受賞しています。

松井今朝子(まつい けさこ) 1953(昭和28)年~
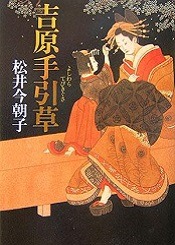 |
松井今朝子は京都生まれの小説家です。早稲田大学大学院を卒業後、松竹株式会社に入社、歌舞伎の制作に携わります。退職後も歌舞伎の演出などを手掛けていましたが、1997年に『東洲しゃらくさし』で小説家デビューしました。同年『仲蔵狂乱(なかぞうきょうらん)』で第8回時代小説大賞を、2007年に『吉原手引草』で第137回直木賞を受賞。その他の作品に『円朝の女』、『芙蓉の干城(ふようのたて)』などがあります。
進学を機会に東京で暮らしていましたが、2010年に大宮に移り住みました。
二〇一〇年の七月に、私は東京から埼玉の大宮という町に引っ越した。地名の由来である氷川神社には全長二キロにも及ぶ立派な参道があり、そこは鬱蒼とする並木に彩られたとてもいい散歩道だ。
引用:『今ごはん、昔ごはん』 松井今朝子/著 ポプラ社 2014年 P36

荻原浩(おぎわら ひろし) 1956(昭和31)年~
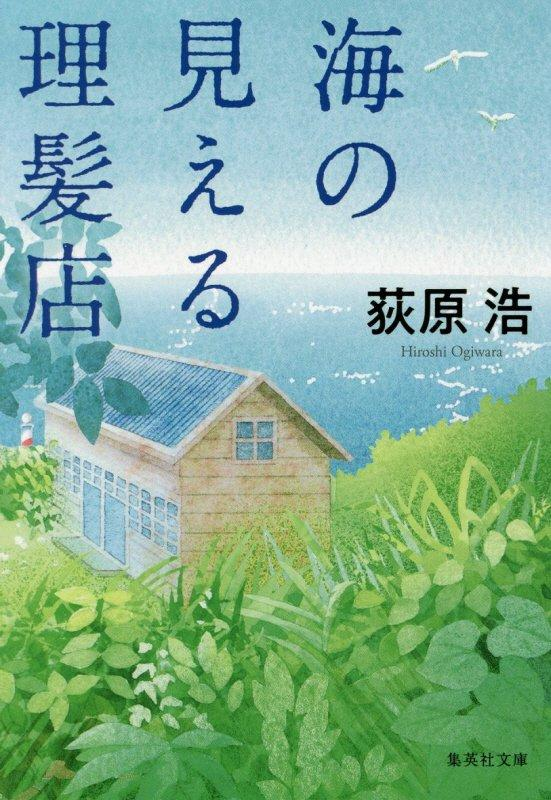 |
荻原浩は大宮市出身の小説家です。1975年、埼玉県立大宮高等学校を卒業しました。
大学卒業後、広告会社に勤務し、フリーのコピーライターを経て、1997年『オロロ畑でつかまえて』で第10回小説すばる新人賞を受賞しました。その後、2005年に『明日の記憶』で第18回山本周五郎賞を、2016年に『海の見える理髪店』で第155回直木賞を受賞しています。
2001年に出版された『誘拐ラプソディー』は、出身地である大宮を舞台に取り上げた、ユーモア、サスペンス要素がある作品となっており、2010年に映画化されました。
「地図から消えてしまった我が故郷、大宮市に愛をこめて」
引用:『誘拐ラプソディー』 荻原浩/著 双葉社 2001年 巻頭

三田完(みた かん) 1956(昭和31)年~
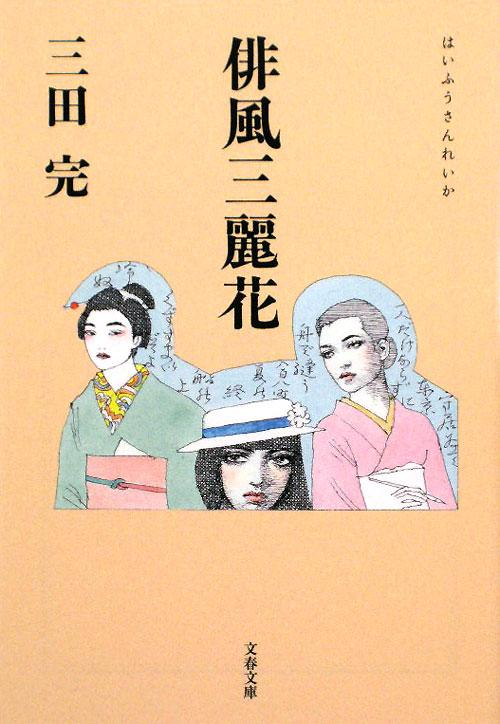 |
三田完は、浦和市生まれの小説家・俳人です。
大学卒業後、NHKに勤務し、テレビディレクター、プロデューサーとして主に歌謡番組の制作に携わりました。退職後は、阿久悠の作詞の仕事を手伝ったり、ラジオ番組「小沢昭一的こころ」の筋書作家の一人として関わったり、多方面で活躍しました。また、俳人としても活動し、俳句結社「水明」に所属していました。俳人・長谷川かな女は、三田の祖母にあたります。
2000年、『櫻川イワンの恋』で第80回オール讀物新人賞を受賞しデビューし、2007年、句会を舞台に描いた小説『俳風三麗花』が、直木賞候補となりました。
その他の著書に『乾杯屋』、『当マイクロフォン』などがあります。

吉田修一(よしだ しゅういち) 1968(昭和43)年~
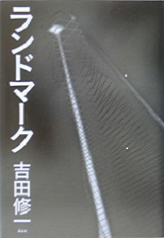 |
吉田修一は長崎県出身の小説家です。
1997年『最後の息子』で小説家デビュー、2002年『パーク・ライフ』で、第127回芥川賞を受賞しました。ほかにも『最期の息子』、『パレード』、『悪人』など、多数の作品を執筆しています。
2004年出版の『ランドマーク』は大宮に建設される地上35階建ての超高層スパイラルビルを舞台にした小説です。大宮駅周辺のビルの様子やさいたま新都心、武蔵浦和などのほか、さいたま市近隣の地名もたくさん登場します。
パチンコ店「Kingdom」は、大宮駅西口そごう裏の、いつか再開発されるのを待ちわびているような、広大な空き地のど真ん中に建っている。
引用:『ランドマーク』 吉田修一/著 講談社 2004年 P3

和田竜(わだ りょう) 1969(昭和44)年~
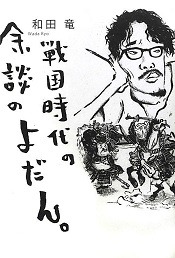 |
和田竜は、大阪府生まれの小説家です。少年時代は広島に、15歳から東京に、そして、2009年頃よりさいたま市に住んでいます。
2003年に映画『忍ぶの城』の脚本で第29回城戸賞を受賞し、2007年、同脚本を小説化した『のぼうの城』で小説家デビューしました。同作品は2012年に映画化され、大ヒットしました。
その他の作品に2014年に第11回本屋大賞と第35回吉川英治文学新人賞を受賞した『村上海賊の娘』や『忍びの国』、『小太郎の左腕』などの歴史小説があります。
15歳からついこの間まで東京に住んでいましたが、最近、埼玉県の浦和というところに引っ越してきました。
引用:『戦国時代の余談のよだん。』 和田竜/著 ベストセラーズ 2012年 P15

九段理江(くだん りえ) 1990(平成2)年~
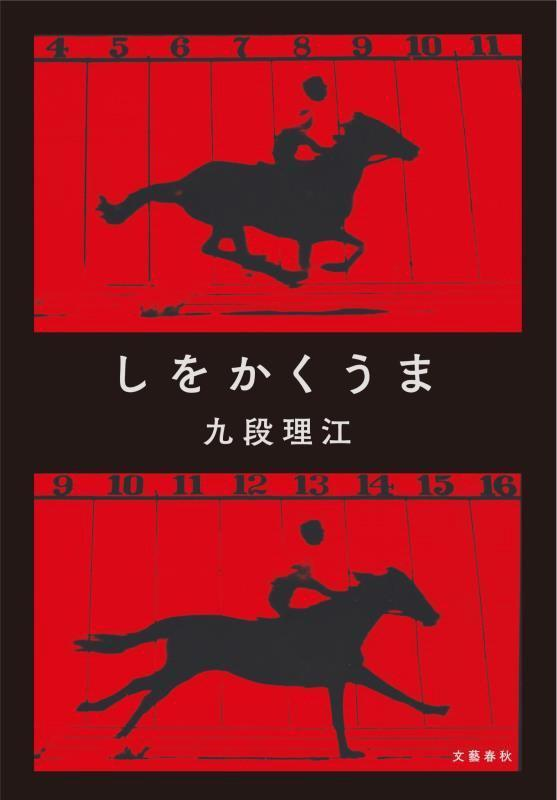 |
九段理江は浦和市出身の小説家です。幼少期と高校・大学時代をさいたま市で過ごし、旧大宮図書館や北図書館をよく利用していたそうです。
2021年に「悪い音楽」で第126回文學界新人賞を受賞し、デビューしました。2023年には前述の作品も収録された『Schoolgirl』で第73回芸術選奨の新人賞を、『しをかくうま』で第45回野間文芸新人賞を受賞しています。
2024年に発表した『東京都同情塔』は、犯罪者は同情されるべきという考え方により、彼らが快適に暮らすための収容施設となる高層タワーが新宿の公園に建てられる未来の日本が舞台です。生成AIを創作に活用したこの作品は、その斬新な世界が生み出すエンターテイメント性や批評性を評価され、第170回芥川賞を受賞しました。

